保護者の声

京都校保護者
1.この学校を選んだきっかけ
我が子と向かい合って「この子に合う学びの形はどんな形だろう」と、公立の教育だけにとらわれずに広い視野で探していた時に、国際バカロレアのPYPに準じたカリキュラムを実践するAIC京都校に出会いました。
我が子に、児童期において何を学んでほしいのかを考えた時、世にある知識や解き方を学ぶのではなく、「学ぶことは楽しい」ということを身をもって学んでほしいと気づき、AICで行なっている、自ら「なぜ(問い)」を見つけて自身に合った方法で答えを探していく探求の学びが、学びを楽しいと感じて自ら伸びゆく人生を作っていける土台を形成するものだ、と思えました。
2.お子様の入学後の変化
我が子が伸び伸び日々を楽しんでいるなと感じます。
みんなと同じであることを強要される環境=みんなと同じであればそれで安心できる環境、ではないため、自分軸の強さと自己肯定感が増していると思います。
また、子どもが純粋に持つ「なぜ?」の発信を後押ししてくれる環境であるため、自分が気になることや、やりたいことにグッとアンテナを立てて行動しワクワクしている我が子の様子は、親として見ていて嬉しくなります。
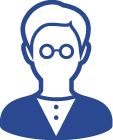
大阪校保護者
1.この学校を選んだきっかけ
私は、変化が激しい新しい時代を生きていく子供たちに、自分自身で考え、物事を組み立て、伝える力をつける学びに、真正面から深く取り組める場がないだろうかと模索し、バカロレアと出会いました。バカロレアの考え方は大人の私でも学びたいと思える視点が幅広く入っており、探していた学びにとてもしっくりきました。
2.お子様の入学後の変化
学校での学びが家庭での生活に繋がり、日常的な対話や経験を通じて学びが深まっていると感じます。
また、「みんなそれぞれ違うし、違っていい。」ということについても、ただ表面的に言葉をインプットするのではなく、様々な角度と様々な場面で、子ども達自身が体験を通して学んでいると感じます。
『みんな違うとは、どういうことなのか?』について、まだ自分の言葉でうまく言語化にできない1年生のうちから、まず体験を通して体と感覚で理解を重ね、その想いや感覚を伝える言葉を徐々につみ重ねていく。まさに、それらを入学当初から取り組んでくださっていると感じます。
概念ってこうして作られていくのだなあと、子どもから学ばせてもらっています。

大阪校保護者
1.この学校を選んだきっかけ
詰込み式・スコア重視の評価方法による従来からの日本の教育の中で育った私にとって、AICの探求心や主体性を重視した教育方法は、とても斬新でした。一方で、本格的に学習をスタートさせるこの時期に、「学び」を我が子がどう捉えるのかについて、慎重だったのも事実です。
体験授業の中で子どもたちが目を輝かせ、授業に意欲的に参加していた様子が印象的だったことから、子どもたちが元来持つ好奇心や興味から導かれた「知りたい」という積極的な学習姿勢が教科書の枠を飛び越えて、多くを学びとることが出来ると確信しました!
2.お子様の入学後の変化
先日、何気なくニュースをみていた時のこと。ふと、「お母さんだったらこんな時どうする?」と息子に聞かれました。突然の問いに慌てつつも、私なりの答えを言うと、息子は全く違う視点で自身の意見をしっかりと述べました。
何気ないやり取りの中に、他者の意見を聞く姿勢、そして自分の意見を伝える力、社会で起きる様々な事柄に興味関心を持っこと、その事柄について「自分事」として考える、といった様々な成長が見られました。
驚く私の傍ら飄々とした様子で、学校ではいつもこんな風に友達や先生と意見を交わすんだと息子は言いました。日常に潜む無数の答えのない問題に自然と向き合うようになった息子を誇りに思うと同時に、AICでの日々の学びに感謝の気持ちでいっぱいになりました!

大阪校保護者
1.この学校を選んだきっかけ
未来の社会を想像し、息子への教育環境を考えた時に日本の画一的な教育手法に対しては疑問しかありませんでした。これからの世の中においては、何事にも主体性や積極性を持ち自ら切り拓いていくチカラが必要だと考えます。英語「で」学ぶこと、そして自らが考え、行動する「考動」の精神がAICでのカリキュラムには凝縮されている点を最も重要視しました。
また1つの科目を注力して学ぶ、記憶力や単一型の内容ではなく、複数教科の融合は、社会に出てからのリアリティ・実践性という意味で、大きく共感する部分です。
2.お子様の入学後の変化
もともと創造性は高い方だと思っていましたが、クリ工イティブな発想がより促進されたと思います。
STEAMを複合的に学ぶ学校生活の中で、自然とそれらに対する探究心が生まれているのだと感じます。
絵画や工作についてもマテリアル(描画や絵の具などの部材)を与えたら、それらをフル活用した上に、自分自身でさらに創意工夫した上で、壮大なアウトプットをするようになったり、興味を持った楽器を与えると、なぜこんな音が出るのか、こうするにはどうすればよいか?と「How」「Why」といった、論理的考察を裏付ける質問が多数出てくるようになりました。
卒業生の声

AICJ(IBディプロマコース 2013年卒)
| ~Profile~ | |
| 2013年 | ミシガン州立大学 進学 |
| IBの成績が大学単位としてカウントされ飛び級で3年で卒業 | |
| 2016年 | 日本国内の衛生用品の機械メーカーへ就職 |
AICJ入学当初、英語スキルは、アルファベットが書けるくらいでした。でも、在学中は、もう一度やり直せるとしても、同じくらい頑張ることはできないだろうなと思うくらい、いろんなことに全力で取り組みました。海外進学は、何かワクワクするものがあったのと、AICJで練習したことを試せる本番がほしいと思ったからです。アメリカの大学へ行くまでは、成績が良い人には自動的に良い機会が与えられると思っていました。
でもそこは少々成績が悪くても積極性がある人がほしいものを手に入れられる世界でした。評価されるのは、自分が求めていることを表現できて、自分から行動できて、自分を売り込める人です。私はその逆だったので、それに気付けてからは、特に心の準備ができてなくてもとりあえず行動できるようになりました。
“Fake it till you make it” というフレーズがあるのですが、できる気がしなくても飛び込んでみていいということを知れたのがアメリカでの良い経験でした。
今社会人となって、自分がなれる一番「すごい」になるという漠然とした目標があります。
具体的には、世界のどこでも通用するスキルとコミュニケーション力を持った、グローバルな機械設計のマスターになりたいです。でも、会社がカリキュラムを作ってくれたり、勉強する時間や設備を与えてくれたりするわけではないので、自分の意志でスキルアップするのは体力も気力も必要です。最近、半年間休職して大学で機械工学の授業を受けました。この歳で大学に行ってみて感じたことは、学生のときに頑張る方が今よりも費やせるエネルギーも大きくて、環境も整っていて、それによって開ける道もたくさんあるということです。
ですから、後輩のみなさんも、今AICJでなり得る「最高のすごい自分」を目指してください。

AICJ(IBディプロマコース 2018年卒)
| ~Profile~ | |
| 2018年 | シンガポール国立大学 進学 |
| 大学在学中は、日本・シンガポールにおけるVC・コンサル・事業会社の計8社で長期インターンシップに従事 | |
| 2023年 | 日本国内の外資系IT企業へ就職 |
大学では熱量の高い学生が世界中から集まる非常に恵まれた環境に身を置くことができましたが、同時に自身の未熟さに時には打ちひしがれながら必死にもがき、無事卒業ができました。勉学以外では、在学中に日本国内・国外の企業8社で長期インターンシップを行い、サークルの立ち上げ、事業の立ち上げなど様々な活動に精力的に挑戦し、非常に濃密な時間を過ごすことができました。
高校を卒業すると、自身で目標設定、意思決定が必要な場面が大きく増えます。大学合格という分かりやすい目標は消え、朝から夜まで授業で埋まっていた予定がなくなります。中学高校までは卒業までの6年間というタイムラインで生きてきた中、いきなり何十年という時間をどう過ごすか問われる気がしてどうしよう・・・と思ったこともあります。
しかし高校生の時からどのような人生にしたいかを考える機会が多く、行動に移せる機会を沢山学校からもらいました。当時の私は社会問題の解決に関心があり、核廃絶や貧困問題に関するイベントを沢山紹介してもらい、学校でチャリティーイベントを開催し、九州で新しいディベートイベントを立ち上げるなど様々な挑戦の相談に乗っていただき、背中を押していただきました。学校による手厚いサポートを通して自主性を育み、自身の人生について考える癖を高校生までに身につけられたことにより、シンガポールで周りから大きな刺激を受けながらも流されることなく有意義な時間を過ごすことができました。
どのような学びを修められるのかは人それぞれですが、何事にも恐れず挑戦して欲しいと思いますし、その背中を押してくれるのがAICJです。勉強、遊びやその他活動を一生懸命全力でやりきましょう! 応援しております。
